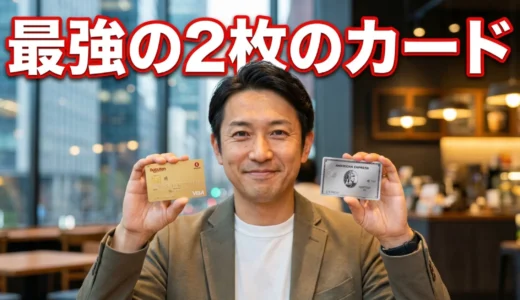上級カード道場では、アフィリエイトプログラムを利用しアコム社などから委託を受け広告収益を得て運用しているため記事中にPRリンクを含みます。ただし、提携の有無が記事内容およびランキングに何ら影響を与えるものではありません。
※保険の適用条件や補償内容は各カード会社により異なります。
※年会費・手数料等の情報は記事作成時点のものです。最新情報は各カード会社の公式サイトでご確認ください。
※ポイント還元率は利用条件により異なります。詳細は各カード会社の公式サイトでご確認ください。
「クレジットカードは何枚持つのがベストなのか」という疑問は、多くの方が抱える悩みです。現在クレジットカードを1枚お持ちの方も、すでに複数枚持っている方も、最適な枚数や使い分け方法について正しい知識を持つことで、より便利でお得なカードライフを送ることができます。
本記事では、最新の統計データをもとにクレジットカードの理想的な枚数から、2枚持ち・3枚持ち・4枚持ちそれぞれの最強組み合わせまで、実践的なアドバイスをお届けします。また、複数枚持ちのメリット・デメリットや信用情報への影響についても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

このサイトの運営者情報
岩田昭男(上級カード道場 編集長)
同大学院修士課程修了後、月刊誌記者などを経て独立。流通、情報通信、金融分野を中心に活動する。主力はクレジットカード&電子マネーの研究で、すでに30年間に渡って業界の定点観測をしている。
主な著書としては、「Suica一人勝ちの秘密」(中経出版・現カドカワ)「信用格差社会」(東洋経済新報社)「信用偏差値」(文春新書)「クレジットカード・サバイバル戦争」(ダイヤモンド社)「ドコモが銀行になる日」(PHP)「キャッシュレス覇権戦争」(NHK出版)、また、クレジットカードのムックも50冊以上監修しキャッシュレスの生き字引として情報発信を続けている。
ウエブは、「岩田昭男の上級カード道場」、まぐまぐでメルマガを毎月二回発行。
記事の信頼性
・クレジットカード研究歴30年以上の専門家が監修
・累計50冊以上のクレジットカードムックを監修
・各カード会社の公式情報を2025年10月時点で確認
・定期的に情報を更新(最終更新:2025年11月17日)
クレジットカードの保有枚数に上限はあるのか

クレジットカードの保有枚数について、法律で定められた上限はありません。審査に通過すれば、理論上は何枚でも保有することが可能です。
ただし、実際には以下の要因が保有枚数を制限する場合があります。
カード会社による制限要因として、年収に対する利用限度額の総額、既存カードの利用状況、申込履歴などが審査で評価されるため、無制限に発行されるわけではありません。
また、管理面での現実的な制約も考慮する必要があります。枚数が増えすぎると利用明細の確認や支払い管理が複雑になり、結果的に使いこなせなくなる可能性があります。
>無制限に使えるクレジットカードを見る

クレジットカードの枚数よりも、利用目的に応じた選択が重要です。

カードの組み合わせだけじゃなく、利用履歴も見直すことが大切よ。
日本人の平均保有枚数は約3枚
一般社団法人日本クレジット協会が公表した最新データによると、2024年3月末時点での国内クレジットカード発行枚数は3億1,364万枚となっています。
これを20歳以上の日本の人口(約1億449万人)で割ると、1人あたり約3.0枚のクレジットカードを保有している計算になります。この数値は年々増加傾向にあり、複数枚持ちがスタンダードになっていることがわかります。
年度別の発行枚数推移を見ると、キャッシュレス化の進展とともに着実に増加しており、多くの人が用途に応じて複数のカードを使い分けていることが読み取れます。
クレジットカード複数枚持ちの5つのメリット

クレジットカードを複数枚持つことで得られる具体的なメリットをご紹介します。これらのメリットを理解することで、自分にとって最適な枚数や組み合わせを見つけることができます。

複数枚保有する際は、各カードの特典を明確に把握して使い分けることが大切です。

カードの特典を使いこなすために、定期的に見直すことが大事ですわね。
カード固有の特典やサービスを幅広く活用できる
各クレジットカードには独自の特典やサービスが付帯されており、複数枚持つことでより多くの恩恵を受けることができます。
特典の種類としては、ポイント還元率の優遇、特定店舗での割引、旅行保険の補償、空港ラウンジの利用権、コンシェルジュサービスなどがあり、カードごとに内容が大きく異なります。
例えば、普段の買い物では高還元率のカードを使い、旅行時には手厚い旅行保険が付帯したカードを選ぶことで、それぞれのシーンで最大限のメリットを享受できます。

特典を最大限に活用するため、使用頻度に応じたカードの組み合わせを考えましょう。

特典は魅力的だけれど、利用条件をしっかり確認しておくことが大事よ。
ポイント還元を最大化できる使い分けが可能
カードごとに設定された優待店舗や高還元カテゴリを把握し、状況に応じて使い分けることで、年間のポイント獲得量を大幅に増やすことができます。
効率的なポイント獲得戦略として、コンビニやスーパーでの日常利用に特化したカード、ネットショッピング専用のカード、ガソリンスタンドでの給油に有利なカードなど、用途別に最適化された組み合わせを作ることが重要です。
実際の利用例として、「Aカードでコンビニ利用時5%還元」「Bカードでネットショッピング時3%還元」「Cカードでガソリン給油時2%還元」といった具合に使い分けることで、1枚のカードのみを使用した場合と比較して年間数万円分のポイント差が生まれることもあります。

利用するカードの特典や条件を定期的に見直すことが大切です。

カードの使い分けは大事だけど、家計全体の管理も忘れないでね。
国際ブランドの使い分けで決済範囲が拡大
異なる国際ブランド(Visa、Mastercard、JCB、アメリカン・エキスプレスなど)のカードを組み合わせることで、より多くの店舗で決済できるようになります。
国内では主要ブランドの加盟店数に大きな差はありませんが、海外では地域によって対応ブランドが限られる場合があります。VisaとMastercardは世界的に広く受け入れられており、JCBは日本や一部アジア地域で強い一方、アメリカン・エキスプレスは高級店やホテルでの優遇が期待できます。

海外旅行前に、店舗での対応ブランドを事前に確認することが大切です。

ブランドによって特典が異なるから、自分に合ったカードを選ぶのがポイントよ。
トラブル時のリスクヘッジが充実
メインカードが何らかの理由で使用できなくなった際の backup として、サブカードが非常に重要な役割を果たします。
想定されるトラブルとしては、カードの磁気不良やICチップの故障、紛失・盗難、利用限度額の超過、システムメンテナンスによる一時的な利用停止などがあります。
特に海外旅行中や重要な支払い時にメインカードが使えなくなると大きな問題となるため、異なるカード会社・異なる国際ブランドのサブカードを持っておくことで、このようなリスクを大幅に軽減できます。

サブカードは利用限度額を分散できる点も考慮しましょう。

異なるブランドのカードを持つことで、安心感が増すのよ。
利用明細の分類で家計管理が向上
用途別にクレジットカードを使い分けることで、支出の分類と家計管理が格段に楽になります。
分類方法の例として、「生活費専用カード」「趣味・娯楽専用カード」「光熱費・通信費などの固定費専用カード」といった具合に分けることで、各カテゴリーの支出額を明確に把握できます。
この方法により、家計簿アプリと連携させれば自動的に支出分類が行われ、月次・年次の予算管理や節約目標の設定がより効率的に行えるようになります。
クレジットカード複数枚持ちの4つのデメリット

メリットが多い複数枚持ちですが、注意すべきデメリットも存在します。これらを理解し、適切な対策を講じることで、デメリットを最小限に抑えながら複数枚持ちの恩恵を受けることができます。

クレジットカードの利用目的を明確にし、無駄な支出を減らすことが大切です。

カードの利用明細を定期的に見直すことで、意外な支出が見えてくるわね。
管理が複雑化し手間が増大
保有枚数が増えるほど、各カードの利用明細確認、支払い日の管理、ポイント有効期限の確認などの作業負荷が増加します。
管理すべき要素として、各カードの請求額と支払い日、ポイント残高と有効期限、年会費の発生時期、各種キャンペーンの適用条件などがあり、これらを適切に把握し続けることが必要です。
対策としては、カード管理アプリの活用、支払い口座の統一、定期的な利用状況チェックの習慣化などを行うことで、管理負荷を軽減できます。

カードの数が増えるほど、利用明細の一元管理がカギです。

ポイントの有効期限を意識しないと、せっかくのポイントが無駄になっちゃうのよ。
年会費負担が累積する可能性
複数の有料カードを保有すると、年会費の総額が家計を圧迫する場合があります。
年会費の考え方として、単純に負担として捉えるのではなく、年会費に対してどれだけの価値(ポイント還元、特典利用など)を得られているかを定期的に評価することが重要です。
コスト最適化のアプローチとして、サブカードには年会費無料のものを選ぶ、年会費以上の価値を得られるカードのみを有料で保有する、利用頻度の低いカードは解約を検討するなどの方法があります。

年会費が高いカードでも、特典を活用できればコスト以上の価値があります。見直しを忘れずに。

年会費が高くても、特典の利用頻度を考えることが大切なのよ。無駄は避けたいわね。
セキュリティリスクの増加
保有枚数が多いほど、紛失・盗難・不正利用などのリスクが高まります。
リスクの具体例として、財布にすべてのカードを入れた状態での紛失、使用頻度の低いカードの不正利用に気づくのが遅れる、暗証番号やログイン情報の混同などが挙げられます。
セキュリティ対策として、持ち歩くカードは必要最小限に留める、定期的な利用明細チェック、カードごとに異なる暗証番号の設定、利用通知サービスの活用などを実践しましょう。

カードの管理アプリを活用し、リアルタイムで利用状況を把握することが重要です。

使わないカードは早めに解約するのが、リスクを減らす秘訣よ。
使いすぎリスクの拡大
複数のカードを持つことで、総合的な利用額を把握しにくくなり、予想以上の支出につながる可能性があります。
使いすぎを防ぐ仕組みとして、月次の利用限度額を低めに設定する、支出予算を事前に決めてカード別に振り分ける、定期的な支出総額の確認などが有効です。
また、各カードの利用明細を統合して管理できる家計管理アプリを活用することで、全体の支出状況をリアルタイムで把握できるようになります。
枚数別!最強の組み合わせと使い分け戦略

実際にクレジットカードを複数枚持つ場合の具体的な組み合わせと使い分け方法を、枚数別に詳しく解説します。

複数カードの利用は明細確認を怠りやすいので、定期的に見直しをしましょう。

使いすぎを防ぐには、カードごとの利用目的をしっかり考えることが大事なのよ。
2枚持ちの最強組み合わせ
2枚持ちは初心者にも管理しやすく、効果的な使い分けが可能な理想的な枚数です。
メインカードの選び方として、日常利用でのポイント還元率が高く、使える店舗が多い汎用性の高いカードを選びましょう。具体的には、コンビニ・スーパーでの還元率が2%以上、年会費が無料または条件達成で無料になるカードが適しています。
サブカードの選び方として、メインカードと異なる国際ブランド、特定分野での高還元(ネットショッピング、ガソリンスタンドなど)、メインカードにない特典(旅行保険、空港ラウンジなど)を持つカードを選択します。
おすすめの組み合わせ例として、「日常利用に強い高還元カード(Visa)+ 旅行特典充実カード(JCB)」や「コンビニ特化カード(Mastercard)+ ネットショッピング特化カード(アメックス)」などがあります。
>クレジットカード最強の2枚を見る

サブカードの特典がメインカードと重複しないか確認することが重要です。

還元率だけでなく、利用シーンを考えた選び方が大切なのよね。
3枚持ちの最強組み合わせ
3枚持ちは用途の細分化により、さらに効率的なポイント獲得と特典活用が可能になります。
基本構成として、「メインカード(日常利用)+ サブカード1(特定分野特化)+ サブカード2(緊急時・特典用)」という形で役割分担を明確にします。
具体的な役割分担例として、メインカードは生活費全般をカバーし、サブカード1は旅行・交通費に特化、サブカード2は光熱費などの固定費やネットショッピングに使用するといった使い分けが効果的です。
3枚それぞれで異なる国際ブランドを選ぶことで、国内外どこでも対応できる体制を整えることができ、リスク分散の観点からも非常に有効です。

サブカードの選定時に、利用限度額や手数料も考慮することが重要です。

カードの特典内容をしっかり比較して、自分に合ったものを選ぶのが大切よ。
4枚持ちの最強組み合わせ
4枚持ちは上級者向けの構成で、細かな用途分けによって最大限の恩恵を受けることができます。
推奨構成として、「汎用メインカード + ネットショッピング専用カード + 旅行・交通専用カード + 固定費・公共料金専用カード」という4分割が効果的です。
管理のコツとして、各カードの利用シーンを厳密に決め、混在させないことで混乱を避けます。また、4枚すべてを持ち歩く必要はなく、外出時には用途に応じて2〜3枚を選択して携帯します。
年会費の負担を考慮し、メインカード以外は年会費無料のカードを中心に構成することで、コストパフォーマンスを最適化できます。
複数枚申込時の注意点と信用情報への影響

クレジットカードを複数枚申し込む際には、信用情報に関する重要な注意点があります。

各カードの特典や利用限度額を定期的に見直し、最適化を図ることが重要です。

カードの利用状況をこまめにチェックして、無駄な手数料を避けることが大切なのよ。
多重申込(申込ブラック)のリスク
短期間(目安として1ヶ月以内)に3枚以上のクレジットカードに申し込むと、「申込ブラック」と呼ばれる状態になる可能性があります。
申込ブラックになる理由として、金融機関は「短期間で複数の与信を求める人は資金繰りに困っている可能性がある」と判断し、審査を慎重に行うか、場合によっては審査落ちさせることがあるからです。
申込情報は信用情報機関に6ヶ月間記録されるため、この期間中は新規カードの審査に通りにくくなります。
適切な申込タイミング
複数枚のカードを作りたい場合は、以下のスケジュールを推奨します。
1枚目のカード申込後、少なくとも1ヶ月、できれば3〜6ヶ月間は利用実績を積んでから2枚目に申し込みましょう。既存カードで良好な利用実績(遅延なし、適度な利用額)を作ることで、次の審査でプラス評価を受けやすくなります。
急ぎでない場合は、6ヶ月以上間隔を開けることで、申込履歴によるマイナス影響を完全に回避できます。
総与信枠への影響
複数のクレジットカードを持つことで、総与信枠(すべてのカードの利用限度額の合計)が年収に対して過大になる可能性があります。
一般的に、総与信枠が年収の3分の1を超えると新規審査に影響すると言われており、これを意識してカードを申し込むか、既存カードの利用限度額を調整することが重要です。
対策として、使わないカードの解約、利用限度額の引き下げ申請、年収アップ時の収入証明書提出などを検討しましょう。
実際の利用者の声
複数枚持ちを実践している方々の体験談をご紹介します。これらの実例を参考に、ご自身にとって最適な枚数や使い分け方法を見つけてください。

与信枠が年収の3分の1を超えると、信頼性が下がることに注意が必要です。

新しいカードを申し込む前に、既存の枠を見直すことが大切よね。
2枚持ち利用者の体験談
30代会社員のAさんは「メインカードで日常の支払いをまとめて管理し、サブカードで旅行時の特典を活用しています。2枚だと管理も簡単で、それぞれのメリットをしっかり活用できています。年間のポイント獲得額は1枚の時と比べて約1.5倍になりました」

サブカードの特典を活用する際、利用限度額や年会費も考慮することが重要です。

メインカードの管理が楽でも、サブカードのメリットを忘れないでね。
3枚持ち利用者の体験談
40代主婦のBさんは「生活費用、固定費用、趣味用の3枚に分けることで家計管理が格段に楽になりました。それぞれのカードで得意分野が違うので、使い分けることで年間3万円分のポイントを獲得できています。ただし、ポイントの有効期限管理だけは注意が必要ですね」

カードの特性を理解し、適切な利用方法を見極めることが重要です。

ポイントの有効期限を管理するために、リマインダーを設定するといいわね。
4枚持ち利用者の体験談
50代経営者のCさんは「ビジネス用と個人用を分け、さらに用途別に細分化しています。管理は少し大変ですが、それぞれのカードの特典を最大限活用することで、年間10万円以上の価値を得ています。特に出張が多いので、旅行関連の特典は非常に重宝しています」
カード枚数を減らすべき判断基準と整理方法
複数枚のクレジットカードを持っていても、すべてを有効活用できていない場合は整理を検討しましょう。

特典を最大限活用するには、各カードの利用状況を定期的に見直すことが大切です。

自分のライフスタイルに合ったカード選びが重要なのよね。特典だけでなく、年会費とのバランスも考えてね。
見直しが必要なカードの特徴
年間利用額が10万円未満のカード、年会費の割に特典を活用していないカード、同じような機能・特典の重複したカード、セキュリティ上のリスクを感じるカードなどは整理の対象となります。
また、ポイント有効期限切れが頻発するカード、暗証番号やログイン情報を忘れがちなカードも、管理負荷の観点から整理を検討すべきです。

クレジットカードの特典を定期的に見直し、価値があるか再評価することが重要です。

年会費と特典のバランスを考え、無駄を省くことが大切なのよ。
効果的な整理手順
まず、過去1年間の各カードの利用実績を確認し、年会費や維持コストに対する価値を評価します。次に、各カードの特典や機能を比較し、重複している部分を洗い出します。
その上で、より価値の高いカードを残し、利用頻度の低いカードや重複機能のカードを解約候補とします。解約前には、貯まっているポイントの使い切り、自動引き落としの変更手続きを忘れずに行いましょう。

カードの特典は年々変わるため、定期的な見直しが重要です。

解約後の影響を考えて、クレジットスコアの変化にも注意してね。
解約時の注意点
クレジットカードを解約すると、そのカードで貯めたポイントは原則として失効します。解約前にポイントを使い切るか、可能であれば他のポイントに交換しておきましょう。
また、公共料金などの定期支払いを設定している場合は、事前に支払い方法を変更する必要があります。解約後にこれらの支払いが滞ると、信用情報に悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。
さらに、長期間保有していたカードを解約すると、クレジットヒストリー(信用履歴)が短くなる場合があるため、この点も考慮して解約の判断を行いましょう。
クレジットカードの理想的な枚数のまとめ
クレジットカードの理想的な枚数は、個人のライフスタイルや管理能力によって異なりますが、一般的には2〜3枚が最も実用的で効率的です。
重要なポイントとして、単純に枚数を増やすのではなく、それぞれのカードの特徴を理解し、用途を明確に分けることで初めて複数枚持ちのメリットを最大限に活かすことができます。
また、複数枚申し込む際は信用情報への影響を考慮し、適切な間隔を空けて段階的に取得することが賢明です。定期的にカードの利用状況を見直し、価値を感じられないカードは整理することで、常に最適な構成を維持できます。
最後に、クレジットカードはあくまで支払いの手段であり、ポイントや特典に惑わされて無計画な利用をしないよう、常に計画的な家計管理を心がけることが何より大切です。この記事を参考に、ご自身にとって最適なクレジットカードライフを構築してください。
※カード会社の最新審査基準は非公開となっており、申込み結果は個人の信用状況によります。改定が行われることもあるので、カード会社公式サイトで最新情報を確認しましょう。

解約後のインパクトを理解し、クレジットスコアへの影響を考慮しましょう。

解約手続きの前に、他のカードの特典も見直しておくと良いわね。
・本記事の情報は一般的な情報提供を目的としており、個別の投資や金融商品の推奨を行うものではありません
・カードの審査結果、ポイント還元率、年会費等は各カード会社の判断により決定されます
・最新の情報については、必ず各カード会社の公式サイトでご確認ください
・本記事の情報による損失について、当社では一切の責任を負いかねます